特権階級の無能~「何のためにやるのか?」という目的意識の欠落と、パターン化思考
「愚かすぎた軍事指導者への怒り」保阪正康氏によると、戦前の軍部中枢エリートたちは「何のために、この戦争をするのか?」ということも、「この戦争をいつ、どのように終わらせるのか?」ということも、ほとんど考えていなかったということだ。
はっきり言うが、昭和十年代(とくに二・二六事件以後)の政治、軍事指導者はいずれも平均点以下の人材だ。当時のどの領域にも国際感覚、理念、政治技術、それに軍事観、国家観のいずれをとっても近代日本史のなかで恥ずかしくない人物はいた。たとえば、軍人では駐在武官が長かった山内正文を見よ。彼の軍事観は政治とのバランスのなかに立論されていた。多くの有能な人材がなぜ昭和十年代に指導部に入れなかったか、そこにこそ近代日本の終焉期の愚かしさがあるのだ。
それゆえに〈あの戦争は何だったか〉を考えると悲しくなってくるのだ。なぜ戦うのか、どの段階で鉾をおさめるのか、そんなこと、何ひとつ考えていない軍事指導者たち。歴史の上にどのような意思を刻みこもうとしたのか、などまったく考えてもいない。それゆけ、やれゆけと掛け声をかけ、「戦争とは負けたと思ったときが負け」と自己本位の弁をなし、戦況が悪化すると国民の戦意が足りないからだと言いだし、一億総特攻を呼号する。「この戦争は何のために戦っているのでしょうか」とでもつぶやこうものなら、反戦分子として獄に送られる。
もしあの戦争が、東亜の解放のため西欧植民地主義と戦っている、たとえ我々が敗れてもその理念が実現されるのならそれでいい、自存自給体制を固めるために東南アジアの国々の独立を促し、そしてその資源を対等のビジネスの範囲で受けいれていく、というのならそれはそれでいい。いや十八世紀以後の西欧近代化に対して、日本は中国と連携して東洋文明を対峙させるとでもいうのなら、相応の意味をもたせることはできる。だがそうした理念や目的は何ひとつ明確な形で論じられることはなかった。敗戦のあとにとってつけたようにこうした論を口にする者もいるが、それは“引かれ者の小唄”ではないか。
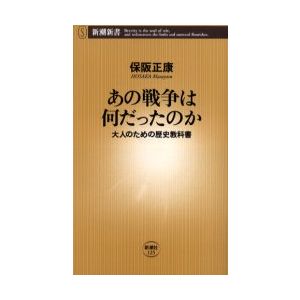
このように、戦前のトップエリートであった軍部中枢は、「いつ、どのように戦争を終わらせるのか?」⇒「何のために、この戦争をするのか?」ということを、ほとんど考えていなかったのである。
『るいネット』「潮流7:暴走する社会」で提起された「特権階級は、肉体的欠乏に発する本当の目的意識を持ち合わせていない」という問題が、戦前の軍部エリートたちの段階で顕在化していたということだ。
彼らは、単に試験制度発の「合格」という無機的な目的意識を植え付けられてひたすら試験勉強に励み、「特権」を手に入れた連中である。しかも彼らの大半は、試験制度という与えられた枠組みの中でひたすら「合格」を目指してきたので、その前提を成す枠組みそのものを疑うという発想が極めて貧弱である。従って、彼らは社会に出てからも、ひたすら既存の枠組みの中で走り続けることになるが、もはやそこでは、既存制度によって与えられた特権の維持と行使という目的以外の目的意識など生まれようがない。
「何のために、やるのか?」という目的意識は、物事を実現するための本来の思考の母胎である。
以下、本来の実現思考の一例である。
①まず、今何を求めようとしているのか。それが全ての幹になる。
⇒②それを実現するために、公式・定理を導き出す。(※この段階ではまだ半答え)
⇒③その公式を使っても、一発で全ての整合が取れる訳ではない。=(半答えの)壁が出てくる。
⇒④どこがダメなのかを考えることが原動力となり、次の公式・定理が生み出せる。
⇒⑤それを繰り返すことで、より整合性の高い公式が生み出せる。
ポイントは、「何のためにやるのか?(何を求めようとしているのか?)」が追求の原点であり、それを前提として、なぜダメなのか、どこがダメなのか考えることが、進化の原動力になるということだ。こうして初めて、新しいものが生み出されるのだ。そういう意味で、逆境こそ進化の源泉である。
ところが、受験エリートに代表されるように、与えられた公式を絶対視してその枠内で何とかしようとする思考が染み付いていると、
・何を求めようとしているのか掴み切れていなくても、進めてしまう。
・壁にぶつかっても、過去に出した公式・定理を絶対視してしまうため、その意味(どういう状況でその公式が作られたのか)を問い直すことをせず、過去の成功パターンでなんとかしようとしてしまう。
このパターン化思考の危険性に、「国際評論家小野寺光一の『政治経済の真実』」も警鐘を鳴らしている。
2009年2月18日 「日本人がだまされやすくなったパターン化思考の勉強法」より引用。
先生はこういっていた。チャート式はだめだね。あれでは、暗記になってしまい、まともに考えられない。
チャート式とは、有名な受験参考書である。それは、問題をパターン化して解こうとする。つまり「こういうパターンの問題が出てきたら、一律にこう考えてみましょう」という海図(チャート)をかかげるやり方」である
今の政治で言えば、「民営化」というキーワードが出たら?→天下りの防止、無駄の排除、自由競争というチャートができるだろう。つまり「良いこと」なのである。
ところが、実態は「民営化」→「合法的な泥棒」のこと。「新たな支配者による利権化」「オリックス」「国民の利益を犠牲にする」「外資と構造改革派が利益を分配」「なぜかオリックスがリース契約」という感じになるだろう。
つまり、チャート式の「パターン化思考」した人たちは、このコイズミ構造改革にイメージでのせられてまんまとはめられる。チャート式では「米国でテロ」→「テロといったら、まず、アルカイダ」「イスラム過激派」などと、すぐに類型した問題はパターン思考にはめられる。
実際に、「米国でテロ」→「本当は自作自演かも」などという、検証はまずできるわけがない。
つまり、日本国民がいま、大規模にだまされているのは、こういった「数学は暗記である」「英文和訳はフィーリングが勝負だよ」「辞書引かなくてもなんとなくわかればそれでいいんだよ」といったような、「自分の頭を使わない」勉強のやり方の犠牲者なのである。
「パターン化思考だから騙される」というのは一面の事実であるが、パターン化思考に染まっているのは大衆ではなく、専ら特権階級の方である。
「特権階級支配を撥ね返した大衆の共認闘争の勝利」で提起したように、国民はもはや世論操作に騙されなくなった。 また、試験制度においてはパターン化思考が最も手っ取り早い勉強法であるのは事実だが、そうである以上、試験制度の勝者ほどパターン化思考が染み付いているということになる。つまり、パターン化思考に染まっているのは、国民ではなく、特権階級の方である。
実際、検察はまたも、民主党小沢幹事長に対して政治資金規正法で挙げようとしているが、それは1年前に失敗した手口である。検察の手口はパターン化しているとしか思えない。また、パターン化思考を要求する(その方が有利である)入試問題を、明治時代から出題し続けていること自体が、大学の学者たちがこの思考の持ち主であることの証左ではないか。
特権階級の無能さの中核にあるのは何か?
「何のためにやるのか?」という本当の目的意識が欠落していることと、パターン化思考しかできないことにあるのではないだろうか。これは、戦前の軍部の時代から現在の検察まで変っていないのではないか? そして、それを生み出しているのは試験制度なのではないか?
いつも応援ありがとうございます。
(本郷猛)


トラックバック
このエントリーのトラックバックURL:
http://blog.nihon-syakai.net/blog/2010/02/1530.html/trackback


hermes handbags tote 日本を守るのに右も左もない | 人々の意識⇔国家(制度)③~略奪闘争と国家成立の起源~