リーマン関連のCDS負債はもみ消されたのか?
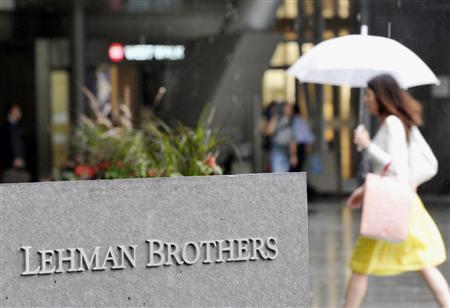
株価が猛反発した理由としてG7によって決定された救済策が市場に一定の安心感を与えたという評価が一般的である。
※詳しい救済策は10/14の記事を参照してください。
G7決定事項→株価急騰の構造 ~世界レベルでの大盤振る舞いではないのか?

これを受けてアメリカ政府は10/14に26億円もの資本注入を金融機関に行うと発表した。融資先も大手9行に1250億ドルと具体的だ。
日本では、三菱UFJが大損覚悟でモルガン・スタンレーを救済した。暴落した株価を高値で買わされた挙句、経営権は持てないという「トンデモ」契約をさせられた三菱UFJの背後には、G7でアメリカ(FRB)の圧力があった、というのが良識ある識者の見解である。
事あるごとに「なりふり構わずあらゆる手で金融機関を救済する」とポールソンは発言していたが、まさになりふり構わず『欧米』金融機関の救済に向けて動き出してきた。
そしてマネーゲーム崩壊の火付け役となったCDSのもみ消しに突入している可能性が高い。

いつも応援ありがとうございます 

10/10は市場関係者で注目の日とされてた。
この日は、リーマン破綻時に保証されるCDSの清算会が開かれた日であった。リーマンが発行した約4,000億ドルの債券は無価値化し、今や約400億ドルに下がっている。清算会によって、CDS発行者は総額3,600億ドルの保険金支払いを義務づけられるといわれ、リーマン関連のCDSをどこがいくら分引き受けたのかによって新たな破綻劇が生まれる可能性があった。
しかし結果的には、CDSの支払額は想定よりかなり低い価格に抑えられたようだ。おそらくCDS関連の負債のもみ消し(談合?)に入ったのではないだろうか?
以下Gamenews.comより引用
【MarketWatch】などが伝えるところによると、先日経営破たんしたアメリカの証券銀行大手リーマン・ブラザーズを対象にした金融派生商品の一つCDS(Credit default swap(クレジット・デフォルト・スワップ))の清算価値が10月10日、国際スワップデリバティブス協会(ISDA、International Swaps and Derivatives Association)のもとで行われたオークションによって元本の8.625%に決定された。オークションそのものは何の混乱も無く進められたとのこと。
今回決定した「元本の8.625%」という値は、リーマン破たん後に暴落した社債の価値などに連動する形で設定されたもの。市場推定では4000億ドル(約40兆円)が保証契約上の元本といわれている。このうち8.625%の価格で買い取られるということは、差し引き91.375%の支払いをCDS発行側が行うことになる(1ドルの保証をしていたCDSの売り手は、そのうち91.375セントをCDSの買い手に支払うということ)。ただしCDS同士や手数料などの相殺もあるので、「実際にはこれらの額のうち2%(8000億円程度)が現金などの形で支払われることになる(once all positive and negative positions are “netted” out, about 2% of that money will actually change hands)」とISDAのCEOであるRobert Pickel氏はコメントしている
以上引用終わり
つまり、本来は4,000億×(100-8.625)%=3,650億ドルをCDS発行側は払う必要があったが、金融機関同士のリスクヘッジや手数料などの相殺によって、その2%(8,000億円)程度で済んだらしい。
たった2%の損失で済んだということで、株価は信頼を取り戻し一気に反発したと思われる。
しかし2%というのは素人目にも非常に少ない。何らかの方法で金融機関同士でCDS関連の負債もみ消し(談合?)に入ったのではないだろうか?

リーマン関連のCDSは10月21日が支払い満期となるため、これが上記発表通りの小額で済むのか、それとも「2%」という値から乖離した負債額となるかは現時点では不明だが、10月末以降破綻した金融機関のCDS清算会が次々と開かれることを考えると、リーマンのCDS処理は今後注目に値する。
※リーマン関連のCDS発行主体はISDAの資料によると、バンクオブアメリカ)、バークレイズ)、BNPパリバ、シティ、クレディスイス、ドイツ銀行、ゴールドマンサックス、HSBC、JPモルガン、メリルリンチ、モルガンスタンレー、UBS、sh-dbcgとされている。
トラックバック
このエントリーのトラックバックURL:
http://blog.nihon-syakai.net/blog/2008/10/866.html/trackback
コメント5件
lived104 | 2009.01.11 15:12
>tennsi21さん
エネルギー事情は、何が一番儲かるか≒市場拡大できるかと言う視点で変化してきたのはその通りですね。
市場拡大信仰から抜け出せば、エネルギー問題は半分解決したと言えます。
あとはこれまでに溜めてきたツケ=環境破壊を修復していく方法を探っていくことですね。
蕗子 | 2009.01.15 22:56
>鎖国政策⇒自給型経済モデルへの転換は、現実的かつ大きな可能性を秘めた選択肢である。
とありますが、鎖国政策する事によって海外の情勢に左右されない国力をつけようというお話ですよね。鎖国政策、といわれて食糧やエネルギーに関してはなんとなくイメージが湧くのですが、書籍やエンターテイメントに関してはイメージが湧きません。それらに関してはどのような形が理想的な状態なんでしょうか。教えて頂きたいです。
lived104 | 2009.01.18 22:36
>蕗子さん
書籍(≒意識生産、一部は解脱充足?)、エンターテイメント(≒解脱充足)の今後のあり方ですね。
意識生産も解脱充足も自給が基本になると思います。
というのは必要となる書籍(意識生産)の中身は、置かれている外圧によって規定されてくるものだからです。
ただ、自然法則の解明など、普遍的な内容に関しては世界で共有していけばいいと思います。
エンターテイメント(解脱充足)については、輸入しなくても全然問題ないように思います。
現実課題に向かう糧としての解脱充足は必要ですが、それは必然的に自給になります。
まったく別の外圧状況で生まれたエンターテイメントを輸入してきても、現実逃避を促進するだけになることが危惧されます。
もし、かみ合っていない回答になっていたらご指摘ください。
yellow hermes bags | 2014.02.01 23:20
hermes audio usa 日本を守るのに右も左もない | なんでや劇場レポート2 ‘08.12.29「金融危機と意識潮流の変化」 ~’09年の経済情勢 貿易収支の変化と鎖国政策という可能性~


資源の活用からいえば地球環境を考えて石炭→石油→原子力に変わってゆくといわれている。でもそれは違う。その時代の市場原理で変わっていっただけである。
見方を変えれば、石炭は200年石油は60年もまだ使える。
さらに海底には今までの2倍以上の石炭・石油・天然ガスの資源がある。
少なくとも石炭・水力に復帰してゆくことでエネルギーは有効に使える。